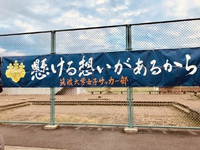2019年01月21日
一般入試(体育専門学群)
こんにちは!体育専門学群1年のくみ(#28)です。
今回は筑波大学体育専門学群一般入試について書かせていただきます。
受験生の皆さん、センター試験本当におつかれさまでした!体育専門学群の試験では、センター試験と、実技小論文による二次試験が5:5の割合です。なので、センター試験が上手くいった人もそうでなかった人も、二次試験で高い点数をもらえるかどうかでまだまだ合格のチャンスも不合格の可能性もあります。悔いの残らないよう、できることは全てやり切って試験に臨むのが大切かなと思います。
私も1年前、センター試験で結構大きなマークミスをしてしまったのですが、二次試験が終わるまで諦めずに対策した結果、なんとか合格することが出来ました。もし何事もなくセンター試験が終わっていて、「多分受かりそう」という中途半端な気持ちで二次試験を迎えていたら、今頃はこのブログを読んでいる側だったかも知れません。
私は陸上競技部だったので主専を陸上競技の走幅跳、副専を卓球で受験しました。参考になるかはわからないですが、一応書いておきます。
主専の陸上競技では、まずみんなで集合した後、今までの自己ベストと競技成績を書く紙を渡されました。この内容がどれほど点数に反映されるかは分かりませんが、私はできるだけインパクトのありそうな競技成績を書きまくりました。アップ時間が与えられ、定刻になると計測がスタートします。試験監督の先生は計測の記録だけではなく、競技している様子を見ながら何か書いていたので単純に計測結果で点数をつけているのではないと思います。
試験対策としては、私は高校の部活に戻って後輩と普通に練習をしていました。けれど、効率を考えて自分の試験種目に特化した方が良かったと思っています。例えば、センター試験が終わってから、体力を戻す時期、筋肉を戻す時期、走力を戻す時期、専門種目の練習をする時期、調整する時期など週ごとにテーマを決めてやってみるのもいいと思います。
副専の卓球は30分くらいのテストでした。受験生同士で練習をした後、大学生と打ち合う試験が始まりました。ホワハンド、バックハンドなどのラリー3分ずつくらいでやって行きました。私は緊張しすぎてミスをしまくりかなり焦っていたので深呼吸を沢山しました。そのあと大学生が打つ下回転のサーブを返し、ラリーをするのですが、回転をめちゃくちゃかけてきます。相当頑張らないと返せないのでしっかりと練習することが大切だと思います。私の相手だった大学生はたまたま、学生選抜かなんかで優勝するようなトップ選手だったので本当にすごい回転でした。返せなくても焦らずに、負けん気でやり返しました。そのあとはゲーム形式が3~4分あります。その時のサーブは受験生からでした。勝てなくて当たり前なので、1点でも負かしてやりたいという勢いでやりました。その頃には試験ということは忘れてトップ選手と卓球できるという貴重な機会を楽しんでいました。何点かとれてすごく嬉しかったのを覚えています。
私は小学校の時に2年間弱、卓球を習っていたので卓球を選びました。ある程度できる自信があればセンター試験のあと、しっかりと練習して勘を身につけるといいと思います。温泉卓球くらいしかやったことが無い場合はあまりやらない方がいい気がします。
論述試験では保健の教科書を一通り読んだ後、そのページごとの内容を要約する練習をしました。ただ覚えるだけではなく、文字にすることが大切だと思います。また、出てくる単語に関してもしっかりと意味を説明できた方がいいです。〇〇は5つ、△△は3つ、これには2種類あるなど、数でまとめてそれを完璧に覚えると勉強しやすいです。また、保健に関しては本番直前の足掻きが意外と効果的だったりします。直前に読んだ文がたまたま出題されるというのはよくある話だと思うので、最後までやり切ってください。本番に私が一番気を付けたのは誤字脱字をしないことです。試験時間ギリギリまでしっかり見直し、センター試験の時と同じ悪夢を繰り返さないようにしっかりと見直ししました。
センター試験前が終わってほっとしてしまうと思いますが、しっかりと1日の使い方を計画し、時間を有効に使ってください。もし自分が試験官だとしたらどんな回答に点数をあげたくなるか、どんなパフォーマンスに目がいくかを考えて本番にそれができるように練習すれば、きっと上手くいくと思います!
最後に筑波大学の創始者であり大河ドラマ"いだてん"でスゴすぎる!と話題になっている嘉納治五郎先生の名言で締めくくっておきます。
"勝って、勝ちに傲ることなく、
負けて、負けに屈することなく、
安きにありて、油断することなく、
危うきにありて、恐れることもなく、
ただ、ただ、一筋の道を、踏んでゆけ。"
頑張ってください!!!
くみ(#28)
今回は筑波大学体育専門学群一般入試について書かせていただきます。
受験生の皆さん、センター試験本当におつかれさまでした!体育専門学群の試験では、センター試験と、実技小論文による二次試験が5:5の割合です。なので、センター試験が上手くいった人もそうでなかった人も、二次試験で高い点数をもらえるかどうかでまだまだ合格のチャンスも不合格の可能性もあります。悔いの残らないよう、できることは全てやり切って試験に臨むのが大切かなと思います。
私も1年前、センター試験で結構大きなマークミスをしてしまったのですが、二次試験が終わるまで諦めずに対策した結果、なんとか合格することが出来ました。もし何事もなくセンター試験が終わっていて、「多分受かりそう」という中途半端な気持ちで二次試験を迎えていたら、今頃はこのブログを読んでいる側だったかも知れません。
私は陸上競技部だったので主専を陸上競技の走幅跳、副専を卓球で受験しました。参考になるかはわからないですが、一応書いておきます。
主専の陸上競技では、まずみんなで集合した後、今までの自己ベストと競技成績を書く紙を渡されました。この内容がどれほど点数に反映されるかは分かりませんが、私はできるだけインパクトのありそうな競技成績を書きまくりました。アップ時間が与えられ、定刻になると計測がスタートします。試験監督の先生は計測の記録だけではなく、競技している様子を見ながら何か書いていたので単純に計測結果で点数をつけているのではないと思います。
試験対策としては、私は高校の部活に戻って後輩と普通に練習をしていました。けれど、効率を考えて自分の試験種目に特化した方が良かったと思っています。例えば、センター試験が終わってから、体力を戻す時期、筋肉を戻す時期、走力を戻す時期、専門種目の練習をする時期、調整する時期など週ごとにテーマを決めてやってみるのもいいと思います。
副専の卓球は30分くらいのテストでした。受験生同士で練習をした後、大学生と打ち合う試験が始まりました。ホワハンド、バックハンドなどのラリー3分ずつくらいでやって行きました。私は緊張しすぎてミスをしまくりかなり焦っていたので深呼吸を沢山しました。そのあと大学生が打つ下回転のサーブを返し、ラリーをするのですが、回転をめちゃくちゃかけてきます。相当頑張らないと返せないのでしっかりと練習することが大切だと思います。私の相手だった大学生はたまたま、学生選抜かなんかで優勝するようなトップ選手だったので本当にすごい回転でした。返せなくても焦らずに、負けん気でやり返しました。そのあとはゲーム形式が3~4分あります。その時のサーブは受験生からでした。勝てなくて当たり前なので、1点でも負かしてやりたいという勢いでやりました。その頃には試験ということは忘れてトップ選手と卓球できるという貴重な機会を楽しんでいました。何点かとれてすごく嬉しかったのを覚えています。
私は小学校の時に2年間弱、卓球を習っていたので卓球を選びました。ある程度できる自信があればセンター試験のあと、しっかりと練習して勘を身につけるといいと思います。温泉卓球くらいしかやったことが無い場合はあまりやらない方がいい気がします。
論述試験では保健の教科書を一通り読んだ後、そのページごとの内容を要約する練習をしました。ただ覚えるだけではなく、文字にすることが大切だと思います。また、出てくる単語に関してもしっかりと意味を説明できた方がいいです。〇〇は5つ、△△は3つ、これには2種類あるなど、数でまとめてそれを完璧に覚えると勉強しやすいです。また、保健に関しては本番直前の足掻きが意外と効果的だったりします。直前に読んだ文がたまたま出題されるというのはよくある話だと思うので、最後までやり切ってください。本番に私が一番気を付けたのは誤字脱字をしないことです。試験時間ギリギリまでしっかり見直し、センター試験の時と同じ悪夢を繰り返さないようにしっかりと見直ししました。
センター試験前が終わってほっとしてしまうと思いますが、しっかりと1日の使い方を計画し、時間を有効に使ってください。もし自分が試験官だとしたらどんな回答に点数をあげたくなるか、どんなパフォーマンスに目がいくかを考えて本番にそれができるように練習すれば、きっと上手くいくと思います!
最後に筑波大学の創始者であり大河ドラマ"いだてん"でスゴすぎる!と話題になっている嘉納治五郎先生の名言で締めくくっておきます。
"勝って、勝ちに傲ることなく、
負けて、負けに屈することなく、
安きにありて、油断することなく、
危うきにありて、恐れることもなく、
ただ、ただ、一筋の道を、踏んでゆけ。"
頑張ってください!!!
くみ(#28)
コメントフォーム